Rental Screening
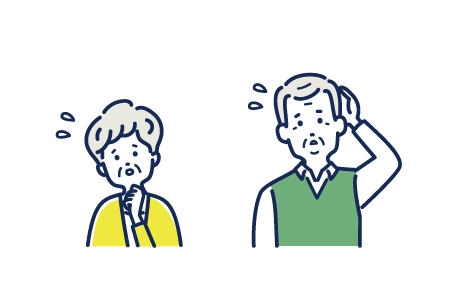
「生活保護だと審査に通らない」と感じたとき、多くの方は“属性の問題”と一括りにしがちです。
しかし実務では、家賃設定の過剰・費用名目の混在・提出書類の不足・支払い運用の不安・生活音やトラブル懸念・連絡体制の不明確さなど、
いくつもの要素が絡み合って不承認になります。
ここを分解し、一つずつ対策することで可決率は着実に改善します。
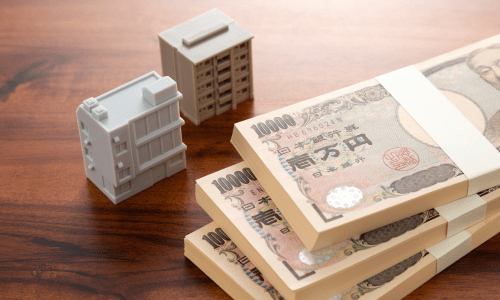
家賃は上限内でも、共益費・管理費・町会費・24Hサポート費などを加えた毎月の確定額が重いと、滞納リスクを懸念されます。さらに実費(電気・ガス・水道・ネット)が高騰すると生活扶助を圧迫。“トータルが回る”証拠を提示できるかが鍵です。セカホゴは家賃等/実費の分離と2,000〜3,000円の余白を設けた家計シミュレーションで安心材料を作ります。
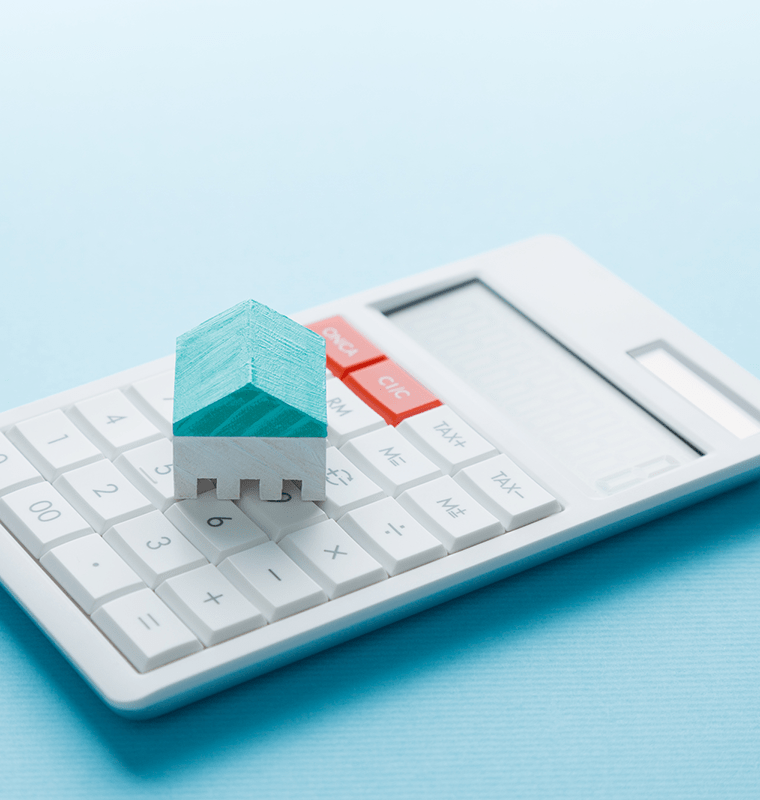
見積や契約書の名目が混在し、領収書が合算一枚だと、住宅扶助や代理納付の運用が不明瞭になり、承認・支払い・監査で詰まります。費目の分離と明細化(家賃/共益費/実費)が、審査を前に進める前提です。

管理会社が怖いのは、トラブル時に見えないこと。騒音・ゴミ・近隣クレームへの初動が遅い入居者像は避けられます。ケースワーカー連絡先・緊急連絡先・入居オリエンテーション・ハウスルール合意書を揃えると、懸念は大きく下がります。

家賃+共益費+管理費=毎月の確定額を先に固めます。光熱費やネットなどの実費は季節変動を見込み、余白2,000〜3,000円を確保。更新料や再契約条件も見越し、長期の総額が上限内に収まる着地を作ります。

見積書・契約条件説明・領収書の名目一致は必須。住宅扶助に該当する費目/実費を明確に分け、収入・支出の根拠資料も整理します。受給証明、住宅扶助見込み、ケースワーカー情報、代理納付合意など、審査側が“確認したい書類”を先出しします。
![]()
家賃は代理納付(家主へ直接支払い)を運用合意して滞納リスクを抑制。入居オリエンテーションでゴミ出し・静音時間・来客ルールを周知し、トラブル未然防止の姿勢を見せます。
審査で問われるのは、月次の回しやすさ。家賃上限にばかり目を奪われず、共益費・管理費・町会費・24Hサポートを加えた確定額を最初に提示します。ここが上限内で安定運用できれば、管理側の不安は大きく和らぎます。
借主としては、連帯保証人の代わりに賃貸保証会社に保証委託料を支払うことで、安心感を得られます。
貸主にとっても、賃貸保証会社が支払いを代行してくれるため、支払い滞納時のリスクが軽減されます。このため、最近では賃貸保証会社の利用を貸主が義務付けるケースも増えています。
「合算・内訳不明」は差し戻しの温床。費目の分離・領収書の明細化をオーナー・管理会社に依頼し、申請→承認→代理納付→領収書管理までブレない導線を作ります。セカホゴはこの書式の型を持ち、管理側の実務負担を軽くすることで、“受け入れやすい申込”に変えます。
敷金・引越し費等は一時扶助の対象になり得ますが、見積の整合・費目の明確化・申請順で可否が左右されます。
家具家電付きや残置相談可の物件は、引越コスト・立ち上げコストを大幅に削減。冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど大型家電が揃うと、生活扶助の余白も確保しやすくなります。

角部屋・戸境壁の厚さ・サッシ性能・換気の良さは、苦情・トラブルの発生率に直結。静音性と清潔感が保ちやすい物件は、管理側の心理的ハードルを下げます。

徒歩10〜15分圏に生活機能が集まる立地は、通院・買物・手続きの負担を下げ、家計・体力の余裕を生みます。

共用部清掃の頻度、ゴミ置き場の管理、夜間のトラブル対応など運営品質が高い物件は、入居後の安定が見通せるため可決率が上がります。
窓口でケースワーカーに相談し、家賃の上限や条件などの確認をします。
不動産会社でお部屋探しをします。生活保護を受けていることを伝え、条件に合う物件を紹介してもらいましょう。
物件が見つかったら不動産会社から初期費用の見積もりを出してもらいます。
不動産会社に出してもらった見積もりと物件の情報ケースワーカーに報告し、了承をもらいます。
了承をもらった上で入居を決めたら、大家さんや管理会社から審査を受けます。
ケースワーカーから初期費用の準備ができる日を聞き、それに合わせて不動産会社と賃貸の契約をする日を決めます。
初期費用を受け取りに行き、不動産会社と賃貸契約を済ませます。契約書と領収書を受け取り、ケースワーカーに提出しましょう。
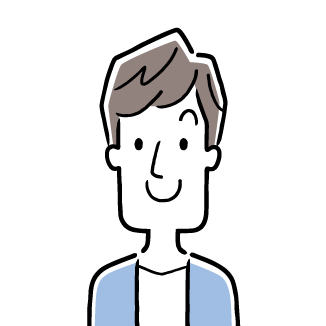
40代・単身(就労移行支援)
上限内・個室鍵付きの駅近シェアハウスへ。費用内訳を分離し事前協議で承認。家賃は代理納付で安定、生活リズムが回復。

30代・単身(初期費用なし)
家具家電付きで引越費用を最小化。ハウスルールの静音時間に納得したうえで入居。交流の適度さが継続の鍵に。

50代・単身(夜勤あり)
夜勤者が複数いる物件を選定し、生活音の時間帯ずれを相互理解。共用部の清掃ルールを徹底し、トラブル無し。

20代・単身(精神科通院)
支援者の訪問に配慮がある運営先を選択。通院動線を優先し、薬局・病院・バス停が近い立地で定着。

60代・単身(見守り希望)
連絡体制と安否確認の仕組みがある物件を選択。防災掲示の充実が安心材料に。

60代・単身(在宅勤務)
リモートワークに必要なネット環境が整っていて安心。持ち込んだデスクで快適に作業でき、共用部での交流が良い気分転換になっています。